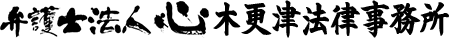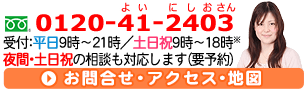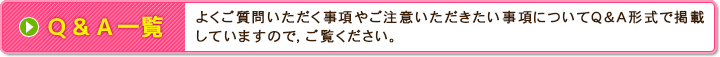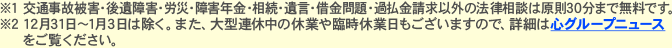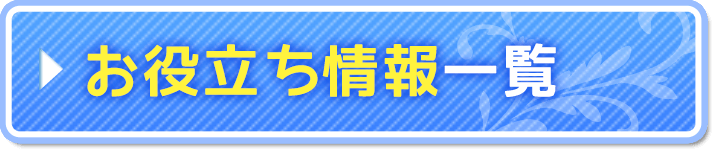遺留分侵害額の計算方法を具体例でわかりやすく解説
遺留分の侵害は、相続で深刻なトラブルに発展する可能性がある問題の一つです。
遺留分侵害額請求をする側・される側ともに、正確な遺留分額・遺留分侵害額を計算したうえで、遺留分問題に対応することが大切になります。
遺留分に関する計算は専門的なので、弁護士に相談しながら正確な計算を行いましょう。
この記事では、遺留分額・遺留分侵害額の計算方法について、具体的なケーススタディを交えながら詳しく解説します。
1 遺留分の算定をするために知っておくべきこと
遺留分の算定をするためには、計算前に知っておくべきことがあります。それは、遺留分侵害額請求をする順番と、遺留分割合です。
⑴ 遺留分侵害額は法定の順位に従って順番に負担する
遺留分侵害額請求が認められた場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた他の相続人から、不足分に相当する金銭の支払いを受けることができます(民法改正前の2019年6月30日までに発生した相続の場合は現物返還が原則です)。
遺留分を侵害する遺贈・贈与が複数存在する場合には、以下の順番に従って受遺者・受贈者は遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項)。
- 遺贈を受けた人
- 死因贈与を受けた人
- 生前贈与を受けた人(※)
※生前贈与を受けた人が複数いる場合には、後から生前贈与を受けた人が先に遺留分侵害額を負担する
遺留分侵害額を負担する上限額は、遺贈・贈与の目的の価額から、受贈者自身の遺留分額を控除した金額になります。
なお、遺留分侵害額請求権に係る債務は、請求を受けた遺留分侵害者が個別に負担します。
つまり、前の順位の遺留分侵害者の資力が不足していたとしても、後の順位の遺留分侵害者に対して不足分を請求することはできません(民法1047条4項)。
⑵ 法定相続人に認められる遺留分割合は?
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条1項)。
法定相続人に認められる遺留分割合は、その構成に応じて、以下のとおりと定められています(同項1号、2号)。
これを総体的遺留分と呼びます。
- 直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
- それ以外の場合:2分の1
なお、相続人が複数の場合には、上記の割合(総体的遺留分)にさらに法定相続分をかけることで、各法定相続人の遺留分割合を計算します(同条2項)。
これを個別的遺留分と呼びます。
また、兄弟姉妹には遺留分がありません。
2 遺留分を計算する際の考え方
遺留分額の計算は、民法に定められたルールに従うことになります。
まずは、遺留分の計算に関する民法上のルールの基本的な考え方を見てみましょう。
⑴ 基礎財産の金額を計算する
遺留分を計算するに当たっては、まず計算のベースとなる財産の総額(基礎財産)を求める必要があります。
基礎財産は原則として、以下の計算式によって求められます(民法1043条1項)。
現実的には、財産の価額評価についても争いになるなど難しい問題があります。特に問題となるのは、額が大きい不動産の場合でしょう。
遺留分算定の基礎となる財産としての不動産評価は、相続開始時を基準とするのが一般的です。
不動産には、固定資産税評価額、相続税税評価額、地価公示価格などいくつかの評価方法がありますが、相続人全員が合意できる評価方法を採用します。
【被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+被相続人が贈与した財産の価額-債務の総額】
なお、生前贈与については、以下のものが遺留分計算の基礎財産に算入されるものとされています。
- 法定相続人に対する生前贈与(民法1044条1項、3項)
-
相続開始前の10年間に行われた、特別受益(民法903条1項)に当たるものに限定。
ただし贈与当時,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年以上前の贈与についても算入されます。
- 法定相続人以外の者に対する生前贈与(民法1044条1項)
-
相続開始前の1年間に行われたものに限定。
ただし贈与当時、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年以上前の贈与についても算入されます。
⑵ 遺留分の金額を求める計算式
遺留分の金額は、次の計算式で求めることができます。
基礎財産×遺留分割合=遺留分の金額
遺留分の金額の具体的な計算例を後述しますので、ご参考にしてください。
3 遺留分額・遺留分侵害額の計算例
上記で解説した遺留分額・遺留分侵害額の計算に関する考え方を前提として、実際に4つの事例を用いて、具体的な遺留分額・遺留分侵害額を計算してみましょう。
⑴ 相続人が子ども2人のみの場合
<設例①>
相続人は子A、Bの2人
遺産(3000万円分)を全額Aに相続させる旨の遺言あり
まずは、遺留分計算の基礎財産を求めます。
設例①における基礎財産は、相続財産の総額に当たる「3000万円」です。
次に、各相続人の遺留分割合を求めます。
相続人はいずれも子であるAとBの2人なので、それぞれの法定相続分は2分の1です。
子のみが相続人である場合、各法定相続人に認められる遺留分割合は、法定相続分のさらに2分の1です。
したがって、AとBの遺留分割合は、いずれも「4分の1」となります。
そして、基礎財産に遺留分割合をかけることによって、AとBの遺留分額はそれぞれ「750万円」となります。
しかし設例①では、3000万円相当の遺産をすべてAに相続させるという遺言があります。
つまり、Bの遺留分「750万円」の全額が侵害されている状態です。
したがって、BはAに対して、750万円の支払いを求めて、遺留分侵害額請求を行うことができます。
⑵ 相続人が配偶者・子ども2人の場合
<設例②>
相続人は配偶者C、子D・Eの3人
遺産(4000万円分)のうち、800万円分をCに、3200万円分をDにそれぞれ相続させる旨の遺言あり(Eには遺産を相続させない)
まずは、遺留分計算の基礎財産を求めます。
設例②における遺留分計算の基礎財産は、相続財産の総額に当たる「4000万円」です。
次に、各相続人の遺留分割合を求めます。
配偶者Cには2分の1、子DとEには4分の1ずつの法定相続分が認められています。
配偶者と子が相続人である場合、各法定相続人に認められる遺留分割合は、法定相続分のさらに2分の1です。
したがって、Cの遺留分割合は「4分の1」、DとEの遺留分割合はそれぞれ「8分の1」となります。
そして、基礎財産に遺留分割合をかけることによって、Cの遺留分額は「1000万円」、DとEの遺留分額はそれぞれ「500万円」となります。
しかし設例②では、Cは800万円しか財産を相続できず、Eは全く財産を相続できていません。
よって、Cには「200万円」、Eには「500万円」の遺留分侵害額が認められます。
この遺留分侵害は、Dが3200万円分の相続をしたことによって生じていますので、Cは200万円、Eは500万円の支払いを、それぞれDに対して請求できます。
⑶ 相続人が配偶者・子ども3人の場合(特別受益あり)
<設例③>
相続人は配偶者F、子G、H、Iの4人
遺産(5000万円分)のうち、1000万円分をFに、4000万円分をGにそれぞれ遺贈する旨の遺言あり(H、Iには遺産を相続させない)
相続開始の3年前に、被相続人からIに対して、特別受益に該当する1000万円相当の贈与が行われた
まずは、遺留分計算の基礎財産を求めます。
設例③における基礎財産は、相続財産の総額である5000万円に、特別受益に当たる生前贈与1000万円を加えた「6000万円」です。
次に、各相続人の遺留分割合を求めます。
配偶者Fには2分の1、子G・H・Iにはそれぞれ6分の1ずつの法定相続分が認められています。
配偶者と子が相続人である場合、各法定相続人に認められる遺留分割合は、法定相続分のさらに2分の1です。
したがって、Fの遺留分割合は「4分の1」、G・H・Iの遺留分割合はそれぞれ「12分の1」となります。
そして、基礎財産に遺留分割合をかけることによって、Fの遺留分額は「1500万円」、G・H・Iの遺留分額はそれぞれ「500万円」となります。
ところが設例③では、Fは1000万円しか遺産を相続できず、Hは全く遺産を相続できていません(Iは1000万円の特別受益を受けているので、遺留分侵害はなし)。
よって、FとHにはそれぞれ「500万円」の遺留分侵害額が認められます。
遺留分の侵害が問題になる遺贈・贈与は、「Gに対する4000万円の遺贈」と「Iに対する1000万円の生前贈与」の2つです。
民法1047条1項1号の規定により、受遺者と受贈者の間では、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。
したがって、FとHはそれぞれ、Gに対して500万円ずつの遺留分侵害額請求を行うことができます。
⑷ 相続人が配偶者・直系尊属2人の場合(第三者への生前贈与あり)
<設例④>
相続人は配偶者J、父K、母Lの3人
遺産は1500万円分、遺言はなし
相続開始の6か月前に、被相続人から愛人Mに対して6000万円分の贈与が行われた
まずは、遺留分計算の基礎財産を求めます。
設例④における基礎財産は、相続財産の総額である1500万円に、特別受益に当たる生前贈与6000万円を加えた「7500万円」です。
Mは法定相続人ではありませんが、生前贈与が相続開始前1年以内に行われているので、持ち戻しの対象となります。
次に、各相続人の遺留分割合を求めます。
配偶者Jには3分の2、父Kと母Lにはそれぞれ6分の1ずつの法定相続分が認められています。
配偶者と直系尊属が相続人である場合、各法定相続人に認められる遺留分割合は、法定相続分のさらに2分の1です。
したがって、Jの遺留分割合は「3分の1」、KとLの遺留分割合はそれぞれ「12分の1」となります。
そして、基礎財産に遺留分割合をかけることによって、Jの遺留分額は「2500万円」、KとLの遺留分額はそれぞれ「625万円」となります。
設例④では遺言がないため、各相続人は法定相続分に従い、1500万円の遺産を分けることになります。
よって、実際に相続できる金額はJが1000万円、KとLがそれぞれ250万円ずつです。
つまり、Jには「1500万円」、KとLには「375万円」ずつの遺留分侵害額が生じています。
この遺留分侵害額を負担するのは、被相続人から唯一の生前贈与を受けた愛人Mです。
したがって、Jは1500万円、KとLはそれぞれ375万円の支払いを、それぞれMに対して請求することができます。
4 詳細な遺留分の計算は弁護士法人心にご相談ください
遺留分の金額を求める際には、民法に定められた手順を正確に守って計算を行う必要があります。
また、相続財産や持ち戻しの対象となる生前贈与などを把握すること自体が難しいケースも多く、正しい請求を行うためには徹底した財産調査が不可欠です。
さらに言えば、遺留分の争いにおいて、基礎財産の価額評価が容易に合意することはあまり多くないため、この点でも専門的な知識が必要になります。
遺留分侵害額請求を受けた側としても、相手の請求が正当なものであるかどうかを正しく判断するためには、上記で解説した考え方を正確に理解したうえで検討しなければなりません。
そのため、遺留分問題への対応には、複雑かつ専門的な検討が要求されます。
もし遺留分問題によってトラブルが生じている・生じそうな場合には、ぜひ当法人にご相談ください。
請求する側・される側のいずれの立場でも、皆様の状況にあわせたアドバイスをいたします。
遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ 遺産分割にお悩みの方へ